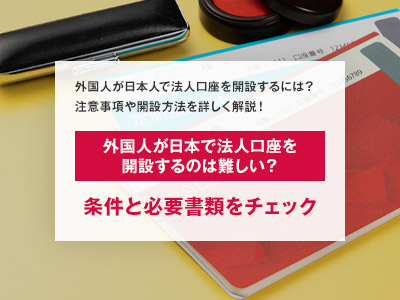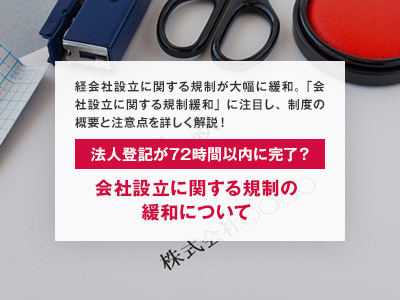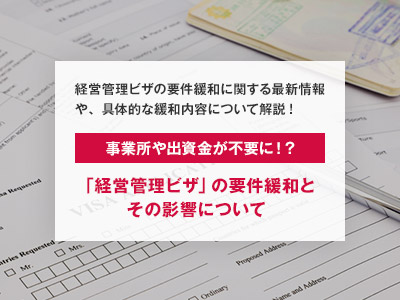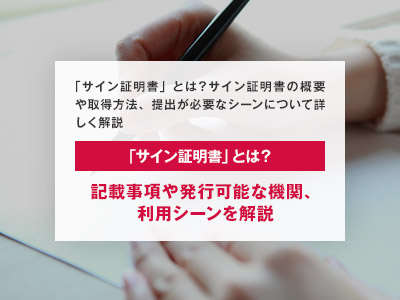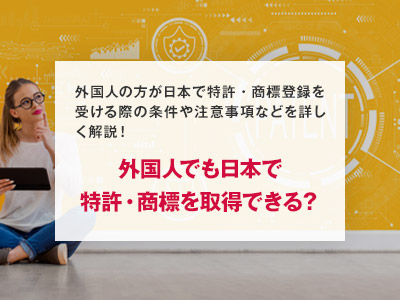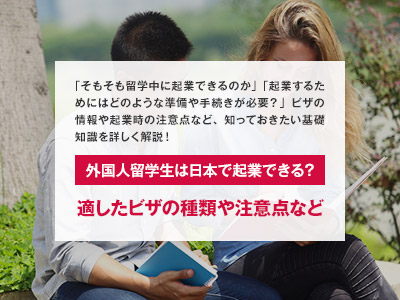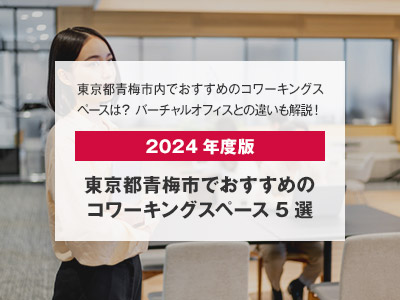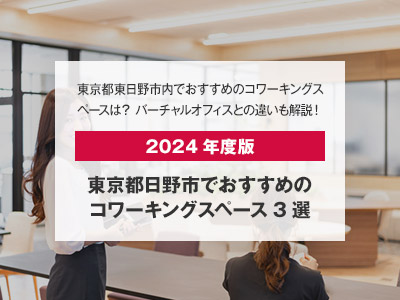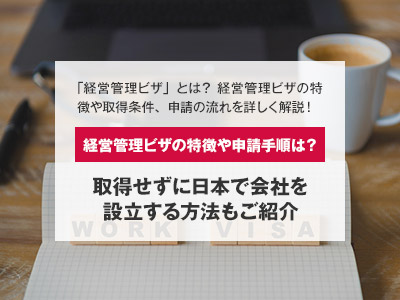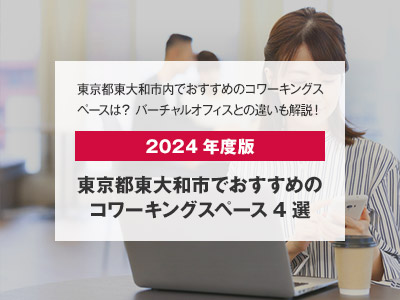「土地家屋調査士」とは?登録方法やバーチャルオフィスを活用するメリットを解説

不動産に関する専門知識を活かして土地や建物の測量・調査を行い、その結果を法務局に申請する役割を担う「土地家屋調査士」。
現場に出向して業務を行う仕事がメインであることから、自宅を拠点に独立開業するケースが増加傾向にあります。
今回は土地家屋調査士の業務内容や不動産鑑定士との違い、登録方法といった基礎知識を解説しながら、自宅を拠点に開業する方におすすめしたい「バーチャルオフィス」の活用メリットについて詳しくまとめました。
土地家屋調査士の仕事に興味をお持ちの方や、費用を抑えた開業を目指している方など、ぜひ参考にしてみてください。
土地家屋調査士とは
土地家屋調査士とは、主に土地や建物に関する調査や測量を行い、登記手続きの代理を務める職業です。
不動産登記法を中心とした法律の専門知識と測量技術を活かし、不動産の適正な管理と取引をサポートする重要な役割を担っており、主に以下のような業務を行います。
土地または家屋の調査および測量
不動産の物理的な状況を正確に把握するため、土地や建物の面積、形状、用途などの測量を行います。
登記申請手続きの代行
所有者に課せられた登記申請義務を代行することも、土地家屋調査士における主要業務のひとつです。
審査請求手続きの代行
登記官による処分が不当であると認められる場合、土地家屋調査士は法務局⾧に対して不服申立てを行います。
筆界特定の手続き
土地の所有者が申請した場合、土地家屋調査士は外部の専門家の意見を踏まえながら筆界(土地と土地の境界線)を特定します。
民間紛争解決手続きの代行
土地の筆界が不明確な場合に生じる民事紛争に関して、弁護士との共同受任によって民間紛争解決手続きを行います。
なお、土地家屋調査士になるためには、年に一度行われる土地家屋調査士の国家試験に合格する必要があります。受験資格は定められておらず、 年齢・学歴問わず誰でも受験可能ですが、合格率は約9~10%と非常に難易度の高い資格試験です。
土地家屋調査士と不動産鑑定士の違いについて
土地家屋調査士の仕事に興味をお持ちの方のなかには、不動産鑑定士と比較検討している場合もあるかもしれません。
土地家屋調査士と不動産鑑定士は「不動産を扱う専門家」という点では共通していますが、それぞれ異なる役割を担っています。
土地家屋調査士は、前述のように土地や建物の測量を行い、不動産の物理的な情報を登記したり、筆界に関するトラブル解決のための筆界特定業務を行ったりする仕事です。
一方、不動産鑑定士は不動産の経済的価値を評価する専門家であり、土地の面積や形状、さらには市場データの収集と分析を行ったうえで物件の市場価値を算出し、不動産の売買や賃貸、相続、担保設定などの際に必要な情報を提供します。
つまり、不動産鑑定士の鑑定作業は土地家屋調査士の測量結果を基に行われることから、土地家屋調査士と不動産鑑定士は実務において密接に連携し、相互に補完し合う関係にあるといえるでしょう。
土地家屋調査士の登録に必要な書類と申請方法
土地家屋調査士試験の合格後は、地域の「土地家屋調査士会」にて登録・入会手続きを行い、税務署に開業届を提出することで事業活動をスタートできます。
土地家屋調査士会への登録・入会に必要な書類
土地家屋調査士会への登録・入会時には、以下の書類の提出を求められることが多いです。
・登録申請書
・証明写真
・身分証明書
・履歴書
・資格証明書
・誓約書
・住民票
・戸籍謄本
・印鑑届
・入会届
・表札申込書
地域によって多少の違いがみられるため、申請を希望する土地家屋調査士会の公式サイトを参照しながら書類の準備を進めることをおすすめします。
土地家屋調査士会の登録・入会にかかる費用
土地家屋調査士の登録・入会にかかる費用相場は以下の通りです。
入会金:約50,000円
共済基金:約30,000円
登録手数料:約25,000円
表札作成代:約13,200円
登録免許税:約30,000円
また、土地家屋調査士会への登録時には、会費の前納を求められることも多いです。たとえば千葉県土地家屋調査士会においては月額会費が15,500円で、登録時に半期分を前納する必要があります。
初期費用だけでも20万円以上かかる計算になるため、あらかじめ金額の詳細を確認したうえでしっかりと資金を準備しておきましょう。
土地家屋調査士会の登録・入会手続きの流れ
土地家屋調査士資格の合格後は、基本的に以下の流れで登録・入会手続きを進めます。
【ステップ1】必要書類を準備する
まずは、前述した必要書類を不備のないように準備します。
【ステップ2】申請先に事前連絡を行う
必要書類が揃ったら、入会しようとしている土地家屋調査士会に事前に連絡を取り、書類提出日を決定します。事前連絡なしでは受け付けてもらえない場合もあるため、必ずアポイントネントを取ったうえで申請手続きを行うことが大切です。
【ステップ3】調査士会にて申請手続きを行う
所定の日に調査士会へ必要書類と所定の手数料を持参し、申請手続きを行います。
【ステップ4】登録完了の通知を待つ
書類の提出が完了した後は、調査士会からの登録完了通知を待ちます。一般的には申請後1週間~2週間程度で通知が届きます。
【ステップ5】税務署に開業届を提出する
土地家屋調査士会への加入手続きが完了したら、開業届を税務署に提出して事業活動をスタートします。
自宅での開業時には「バーチャルオフィス」の利用がおすすめ
土地家屋調査士の主な勤務場所は各現場であるため、自宅兼事務所として独立するケースも少なくありません。自宅であれば家賃などのオフィスコストがかからず、初期費用やランニングコストを大幅に抑えた開業が叶います。
ただし、自宅兼事務所として活動するにあたり、「事務所の所在地=自宅の住所」で登録申請することは避けるほうがよいでしょう。自宅のプライバシーが脅かされるリスクがあるだけでなく、自宅が賃貸の場合は賃貸借契約違反に問われる可能性もあるためです。
そこで、自宅兼事務所にて土地家屋調査士の仕事を行う場合は「バーチャルオフィス」を活用することをおすすめします。バーチャルオフィスとは事業用の住所や電話番号をレンタルできるサービスで、主に以下のような魅力があります。
少ない費用負担で事業用拠点を設けられる
バーチャルオフィスの利用にあたって必要なコストは、5,000円~10,000円程度の登録料と月額数千円ほどの利用料のみです。賃貸オフィスを利用する場合と比較すると、初期費用・ランニングコストともに大幅に抑えられます。
自宅のプライバシーを保護できる
バーチャルオフィスを利用すれば、自宅兼オフィスであっても自宅の住所を公開する必要がありません。自宅のプライバシーを守りながら、安心感を持って事業活動を進められるでしょう。
都心一等地の住所を手軽に利用できる
バーチャルオフィスの拠点は、銀座や青山、渋谷、新宿などの都心一等地に多く所在しています。そのような有名なビジネスエリアにオフィスを構えていると、クライアントに安心感を与えられ、ビジネス活動を優位に進められる可能性があります。
付帯サービスの利用でスムーズな運営を目指せる
バーチャルオフィスでは、郵送物の転送や電話応対、会議室の利用といったオプションサービスを提供していることが多いです。自社に合った付帯サービスを活用することで、各種サポートを得ながらスムーズな運営を目指せます。
まとめ
「土地家屋調査士」とは土地や建物の測量・調査を行う職業で、独立開業するためには国家資格に合格し、地域の土地家屋調査士会にて登録・入会手続きを行ったうえで税務署に開業届を提出する必要があります。
なかには自宅を拠点としてビジネス活動を行うケースも多いですが、その場合に自宅の住所を事務所所在地として登録することはおすすめではありません。プライバシー保護の観点からバーチャルオフィスを活用し、バーチャルオフィスの住所で申請するとよいでしょう。
ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、土地家屋調査士として安全かつコストを抑えた開業を目指してはいかがでしょうか。
記事を探す
- 03局番電話番号
- FAT
- M&A
- NPO法人
- SDGs
- アンケート
- インバウンド
- クラウドファンディング
- コワーキングスペース
- サイン証明書
- サスティナブル
- シニア起業
- ツール
- テレワーク
- トラブル
- トランクルーム
- ドッグトレーナー
- バーチャルオフィス
- ビザ
- フリーランス
- ベンチャーキャピタル
- ペットシッター
- ペットホテル
- マイクロ法人
- マンション建て替え
- マンション敷地売却制度
- レンタルオフィス
- レンタルスタジオ
- ローン
- ワーケーション
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 不動産投資
- 不動産投資コンサルタント
- 中小企業診断士
- 事業売買
- 事業継承
- 会社設立
- 会社設立72時間
- 個人事業主
- 副業
- 創業支援
- 労務
- 商標権
- 商標登録
- 国際法務
- 国際税務
- 土地家屋調査士
- 地方創生
- 地方在住
- 地方移住
- 増資
- 士業
- 変更登記
- 外国人
- 外国人留学生の起業
- 女性起業
- 子会社
- 学生起業
- 定款作成
- 審査
- 就労ビザ
- 弁理士
- 役員住所変更
- 役員変更
- 役員氏名変更
- 後継者
- 日本支店
- 日本進出
- 東京都あきる野市
- 東京都三鷹市コワーキングスペース
- 東京都世田谷区コワーキングスペース
- 東京都中央区コワーキングスペース
- 東京都中野区コワーキングスペース
- 東京都八王子市コワーキングスペース
- 東京都北区コワーキングスペース
- 東京都千代田区コワーキングスペース
- 東京都台東区コワーキングスペース
- 東京都吉祥寺コワーキングスペース
- 東京都品川区コワーキングスペース
- 東京都国分寺市コワーキングスペース
- 東京都国立市コワーキングスペース
- 東京都墨田区コワーキングスペース
- 東京都多摩市コワーキングスペース
- 東京都大田区コワーキングスペース
- 東京都小平市コワーキングスペース
- 東京都府中市コワーキングスペース
- 東京都新宿区コワーキングスペース
- 東京都日野市コワーキングスペース
- 東京都昭島市コワーキングスペース
- 東京都杉並区コワーキングスペース
- 東京都東久留米市コワーキングスペース
- 東京都東大和市コワーキングスペース
- 東京都板橋区コワーキングスペース
- 東京都江戸川区コワーキングスペース
- 東京都江東区コワーキングスペース
- 東京都清瀬市コワーキングスペース
- 東京都渋谷区コワーキングスペース
- 東京都港区コワーキングスペース
- 東京都町田市コワーキングスペース
- 東京都目黒区コワーキングスペース
- 東京都立川市コワーキングスペース
- 東京都練馬区コワーキングスペース
- 東京都羽村市コワーキングスペース
- 東京都葛飾区コワーキングスペース
- 東京都西東京市コワーキングスペース
- 東京都調布市コワーキングスペース
- 東京都豊島区コワーキングスペース
- 東京都足立区コワーキングスペース
- 東京都青梅市コワーキングスペース
- 法人化
- 法人口座開設
- 法人成り
- 海事代理士
- 海外企業
- 海外在住
- 海外移住
- 特許
- 登記情報
- 登記簿謄本
- 目的変更
- 相続
- 社会保険
- 社労士
- 私設私書箱
- 移転登記
- 第一種動物取扱業
- 節税
- 納税管理人
- 経営管理ビザ
- 自宅マンションで登記
- 自社所有拠点
- 著作権
- 融資
- 貸し会議室
- 費用相場
- 資産管理会社
- 資金調達
- 起業スクール
- 重任登記
- 閉鎖(廃業)
- 開業
- 駐在員事務所