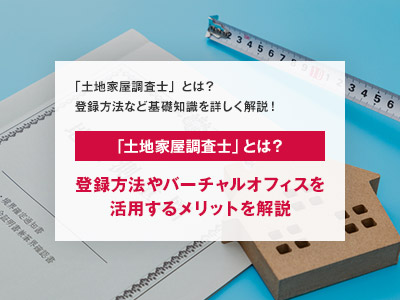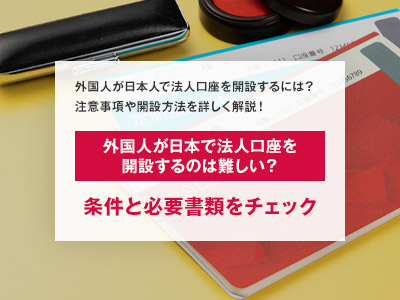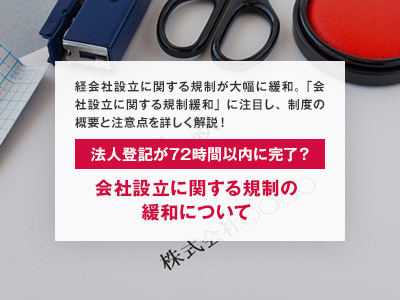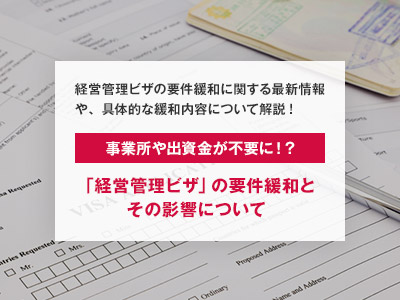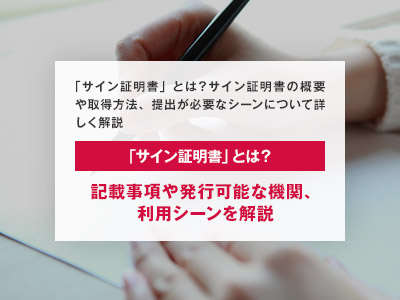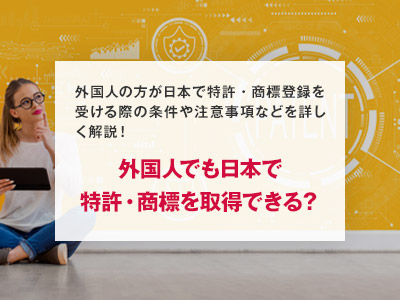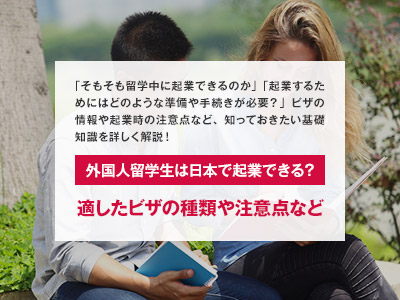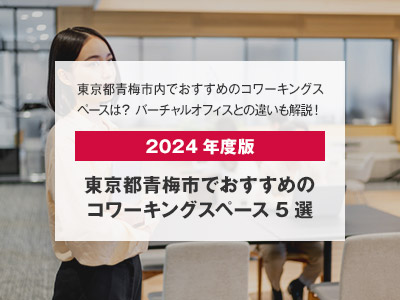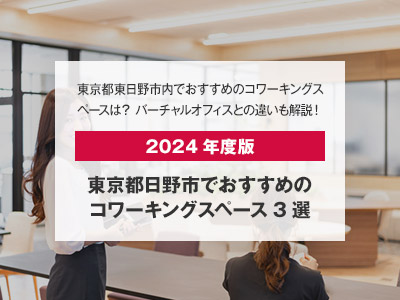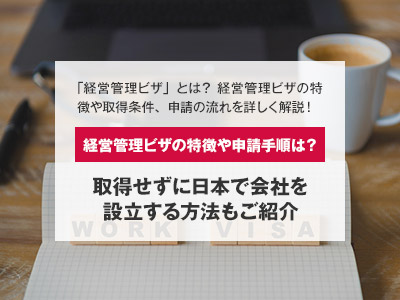生成AIで手軽に起業できる!?活用のポイントと注意点

テキストや画像、音声など、さまざまなコンテンツを自動的に生成する人工知能技術である「生成AI」。
なかでも公開からわずか2か月で1億ユーザーにまで成⾧したOpenAI社の「ChatGPT(チャットジーピーティー)」が有名で、近年はこういったAIツールを活用して起業するケースが急速に増えてきています。
そこで、今回は生成AIの特徴や主なサービス、利用方法などの基礎知識に触れながら、起業時に活用するメリットと注意点についてまとめました。
また、「自宅を拠点にビジネスをスタートしたい」とお考えの方におすすめしたいサービスとして「バーチャルオフィス」を挙げ、活用の魅力を詳しくご紹介します。ぜひ参考にしてください。
生成AIとは
生成AIは「Generative AI(ジェネレーティブAI)」とも呼ばれ、新しいコンテンツを自動生成できる人工知能技術のことを指します。
従来のAIは与えられたデータをもとに分析や予測を行い、適切な回答を探して提示する性質が特徴的ですが、生成AIは大量のデータから学習し、そこからパターンを抽出して新しい情報を生成することが可能です。
これにより、テキストや画像、音声、音楽、動画といった多種多様な形式のコンテンツを手軽に作り出せることから、生成AIは金融、医療、エンターテイメント、広告など、さまざまな業界で活用されています。
話題の「ChatGPT」とは
ChatGPTは、米国のAI研究企業であるOpenAI社によって開発された生成型AIチャットボットで、自然な会話を生成できるAIモデルであることが大きな特徴です。
GPT(Generative Pre-trained Transformer)という技術によって膨大なテキストデータを学習し、その情報に基づいて新しい文章を生成する仕組みに基づいています。
ChatGPTが持つ主な機能は以下の通りです。
ユーザーとの会話
ユーザーからのテキスト入力に基づき、自然な会話形式で返答を生成する能力を持っています。そのため、人間同士で行うような質疑応答や雑談が可能です。
テキスト生成
メール・契約書の文面や記事、物語、業務マニュアルなど、さまざまな形式のテキストを生成することもChatGPTの得意分野です。
その際には、ユーザーの指示に応じた特定のトーンやスタイルでコンテンツを作成することもできます。
翻訳
ChatGPTには、異なる言語間でテキストを翻訳する機能もあります。
要約
⾧文のテキストを要約する機能も持っており、学術論文やレポート、メールの内容などを簡潔にまとめることが可能です。
プログラミング支援
ChatGPTはプログラムコードの生成やエラーチェックなども可能で、エンジニアの作業効率を向上させるツールとしても利用されています。
アイデア出し
ユーザーが新しいアイデアや視点を必要とする際に、ブレインストーミングの補助をすることができます。
この機能は、マーケティング戦略や製品開発などの場面で役立ちます。なお、ChatGPTはさらに進化を続けており、最新モデルの「ChatGPT-4o(フォーオー)」では音声および画像の認識機能が格段にアップしました。
また、回答精度も向上しており、より自然な対話が可能となっています。
ChatGPT以外の生成AIサービス
近年、様々な生成AIサービスが登場しており、ChatGPT以外にも多くの優れた対話型AIが存在します。
ここではChatGPTと同じ「総合型」をはじめ、「翻訳特化型」、「要約特化型」、「マーケティングライティング」、「コーディング支援」のカテゴリ別に主な生成AIサービスをピックアップしました。
| 特徴 | 主なサービス名 | |
|---|---|---|
| 総合型 | テキストや画像、音声、動画、コード生成などの多様な機能を統合した生成AIサービス |
・Claude ・Google Gemini ・Perplexity AI ・Microsoft 365 Copilot |
| 翻訳特化型 | 主に自然言語処理(NLP)技術 に基づいて構築されており、複 数の言語間で正確かつ自然な翻 訳を提供する生成AIサービス |
・DeepL ・Google翻訳 ・Microsoft Translator |
| 要約特化型 | 自然言語処理(NLP)を用いて テキストの重要なポイントを抽 出し、簡潔に表現する生成AI サービス |
・Smart書記 ・User Local 自動要約ツール |
| マーケティングライティング | 主に自然言語処理(NLP)と機 械学習を駆使して、テキストコ ンテンツを自動生成する生成AI サービス |
・Jasper ・Copy.ai ・Writesonic |
| プログラミング支援 | 主に自然言語処理(NLP)と機 械学習(ML)を活用して、開発 者が入力した指示や質問に対し て自動的にコードを生成するAI サービス |
・GitHub Copilot ・OpenAI Codex ・Amazon CodeWhisperer ・AI Programmer ・Code Llama |
生成AIの利用方法
生成AIの利用にあたって最も重要な作業が、「プロンプト」と呼ばれる指示文の入力です。具体的かつ明確なプロンプトを提供することで、AIからの応答の質が向上します。
たとえば「生成AIについて教えて」といった漠然としたプロンプトではなく、「生成AIの基本的な機能と活用方法について説明して」と詳細に入力するほうが、ニーズに合った応答を得やすくなります。
なお、一度のプロンプトで理想的な回答が得られない場合は、追加の質問を入力するとよいでしょう。明確な指示を繰り返し提供することで、目的に合ったコンテンツが生成されやすくなります。
AIに代替される可能性がある職業は?
株式会社クロス・マーケティングが、2023年5月に全国20~69歳の男女有職者7,532
名を対象に実施した「生成AIに関する調査(2023年)」によると、
“とってかわられると思う職業”の上位は「財務・会計・経理」と「一般小売店の店員」で、それぞれ全体の約2割を占めました。次いで多かったのが「運転手」で19%、そのあとに「データサイエンティスト(18%)」や「システム・サイト保守運用(18%)」が続きます。
一方、“とってかわられないと思う職業”においては「農業・漁師」がトップで23%。次いで「医者・看護師・歯科衛生士」が21%、「経営者」が20%、「介護士」が19%でした。
これらの結果から、一般的に「ルーチンワーク・単純作業の多い職業や情報の整理・分析を主とする職業はAIに代替されやすく、逆に対人コミュニケーションが重要な職業や高度な専門知識・判断力が必要な職業はその危険性が低い」と考えられていることがうかがえます。
参考:Cross Marketing「生成AIに関する調査(2023年)浸透状況編」
生成AIを活用して起業するメリット
生成AIの技術が進化する中、起業においてその活用が注目されています。以下に、生成AIを活用することで得られる主なメリットを3つご紹介します。
【メリット1】業務効率化を図れる
生成AIを活用すると多くの業務プロセスを自動化でき、業務効率化を図ることが可能です。たとえば顧客対応や資料作成、データ分析などの定型業務をAIに任せることで、 経営者や従業員はよりクリエイティブな業務や戦略的な仕事に集中することができ、少ない人数でも効率的な経営を目指せます。
【メリット2】起業コストを削減できる
初期投資や運営コストを抑えられることも、起業時に生成AIを活用するメリットのひとつです。たとえばコンテンツ作成やマーケティング活動で生成AIを活用すれば、広告素材やWebコンテンツを迅速かつ低コストで生産でき、専門家に依頼するコストを省くことができます。
また、カスタマーサポートにおいてAIチャットボットを用いることで人的コストも削減でき、経済的にゆとりを持たせた状態でビジネス活動を進められます。
【メリット3】新しいアイデアを効率的に創出できる
生成AIは大量のデータを分析し、過去の事例やトレンドから新たな顧客心理を引き出すことが得意です。そのため、従来の発想にとらわれない個性的かつ斬新なアイデアが生まれやすくなります。
市場のニーズが変化する中で柔軟に戦略を調整でき、さらにはアイデア生成に必要な人力や時間を大幅に削減できることは、起業時において強力な武器となることでしょう。
生成AIを活用して起業する場合に気をつけたいリスク
生成AIをビジネスの立ち上げ時に活用することは、前述のようなメリットがある半面、いくつかの注意点も存在します。具体的にどのようなリスクがあるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
【リスク1】情報の漏えいとプライバシー侵害
生成AIを利用する際に最も気をつけたいのが、情報の漏えいとプライバシーの侵害です。多くの生成AIでは入力データを学習素材として使用することから、機密情報が漏洩するリスクがあります。
そこで、生成AIサービスへの機密情報の入力を避けるとともに、使用するAIサービスのセキュリティ対策をしっかりと確認したうえで導入することが大切です。
【リスク2】ハルシネーション
ハルシネーションとは、AIが実際には存在しない情報や事実に基づかないデータを生成する現象を指します。誤情報と気づかずに利用すると、顧客からの信頼を失ったり、法的な問題へと発展したりする恐れがあるため、AIが出力したデータを人間が確認するプロセスを設けることをおすすめします。
【リスク3】著作権侵害
生成AIの活用時には、著作権侵害のリスクにも注意が必要です。著作権とは創作された表現物を他人が勝手に使えないようにする権利のことで、もしもAIが他の著作物に類似したコンテンツを生成し、それに気づかずに著作権者の許可なしに使用してしまった場合、著作権侵害が問われる可能性があります。
そのため、生成AIが作成した内容に法的な問題がないか、事前にしっかりと確認することが大切です。
自宅での開業時には「バーチャルオフィス」の利用がおすすめ
生成AIを活用した起業に興味をお持ちの方のなかには、「自宅兼オフィス」でビジネス活動を始めることを検討しているケースもあるでしょう。その場合にぜひおすすめしたいのが、事業用の住所や電話番号の貸出しサービスを提供している「バーチャルオフィス」です。
自宅での開業時にバーチャルオフィスを利用することで、以下のようなメリットを得られます。
オフィスコストを軽減できる
バーチャルオフィスの利用にあたってかかる費用は、5,000円~10,000円程度の登録料と月額数千円ほどの利用料のみです。従来の賃貸オフィスに必要な敷金や礼金、光熱費といったコストを削減できるほか、月々の高額な家賃支払いも発生しないため、経済的負担の大幅な軽減が叶います。
自宅のプライバシーを保護できる
バーチャルオフィスを利用すれば、公共の登記情報として自宅住所が公開されることを回避できます。自宅のプライバシーをしっかりと保護できれば、自宅兼オフィスであっても安心感を持ってビジネス活動に注力できるでしょう。
都心一等地の住所を手軽に利用できる
バーチャルオフィスの住所は都心一等地に多く点在しており、知名度の高いビジネス街の住所を手軽に利用できることもおすすめポイントです。
そのような住所に拠点があれば顧客や取引先に対して安心感を与えられ、起業当初から円滑な事業運営を行える可能性があります。
オプションサービスの利用でスムーズな運営を目指せる
多くのバーチャルオフィスは、郵送物の転送や電話応対、会議室利用、会社設立支援といったオプションサービスを提供しています。
必要に応じて活用することで、よりスムーズに起業準備や事業活動を進められるでしょう。
まとめ
新しいコンテンツを自動生成できる生成AIを活用すれば、低コストで事業をスタートし、迅速な成長を目指せます。
目的に応じた適切なAIツールを選定し、AIと人の強みを活かした業務分担によって事業活動を行うことで、より効果的なビジネス展開が可能になるでしょう。
ただし、生成AIには情報漏えいや著作権侵害、誤生成といったリスクなどがある点に注意が必要です。
セキュリティ対策をしっかりと講じたり、AIの出力内容を慎重にチェックしたうえで使用したりと、安全性に配慮した活用を徹底するとよいでしょう。
また、自宅での起業時には「バーチャルオフィス」を活用することで、自宅のプライバシーも保護しつつ、経済的・効率的な事業運営を目指せます。
ぜひ生成AIやバーチャルオフィスといった便利なサービスを有効活用し、新たなビジネスを賢く創造していきましょう。
記事を探す
- 03局番電話番号
- ChatGPT
- FAT
- M&A
- NPO法人
- SDGs
- アンケート
- インバウンド
- クラウドファンディング
- コワーキングスペース
- サイン証明書
- サスティナブル
- シニア起業
- テレワーク
- トラブル
- トランクルーム
- ドッグトレーナー
- バーチャルオフィス
- ビザ
- フリーランス
- ベンチャーキャピタル
- ペットシッター
- ペットホテル
- マイクロ法人
- マンション建て替え
- マンション敷地売却制度
- レンタルオフィス
- レンタルスタジオ
- ローン
- ワーケーション
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 不動産投資
- 不動産投資コンサルタント
- 中小企業診断士
- 事業売買
- 事業継承
- 会社設立
- 会社設立72時間
- 個人事業主
- 副業
- 創業支援
- 労務
- 商標権
- 商標登録
- 国際法務
- 国際税務
- 土地家屋調査士
- 地方創生
- 地方在住
- 地方移住
- 増資
- 士業
- 変更登記
- 外国人
- 外国人留学生の起業
- 女性起業
- 子会社
- 学生起業
- 定款作成ツール
- 審査
- 就労ビザ
- 弁理士
- 役員住所変更
- 役員変更
- 役員氏名変更
- 後継者
- 日本支店
- 日本進出
- 東京都あきる野市
- 東京都三鷹市コワーキングスペース
- 東京都世田谷区コワーキングスペース
- 東京都中央区コワーキングスペース
- 東京都中野区コワーキングスペース
- 東京都八王子市コワーキングスペース
- 東京都北区コワーキングスペース
- 東京都千代田区コワーキングスペース
- 東京都台東区コワーキングスペース
- 東京都吉祥寺コワーキングスペース
- 東京都品川区コワーキングスペース
- 東京都国分寺市コワーキングスペース
- 東京都国立市コワーキングスペース
- 東京都墨田区コワーキングスペース
- 東京都多摩市コワーキングスペース
- 東京都大田区コワーキングスペース
- 東京都小平市コワーキングスペース
- 東京都府中市コワーキングスペース
- 東京都新宿区コワーキングスペース
- 東京都日野市コワーキングスペース
- 東京都昭島市コワーキングスペース
- 東京都杉並区コワーキングスペース
- 東京都東久留米市コワーキングスペース
- 東京都東大和市コワーキングスペース
- 東京都板橋区コワーキングスペース
- 東京都江戸川区コワーキングスペース
- 東京都江東区コワーキングスペース
- 東京都清瀬市コワーキングスペース
- 東京都渋谷区コワーキングスペース
- 東京都港区コワーキングスペース
- 東京都町田市コワーキングスペース
- 東京都目黒区コワーキングスペース
- 東京都立川市コワーキングスペース
- 東京都練馬区コワーキングスペース
- 東京都羽村市コワーキングスペース
- 東京都葛飾区コワーキングスペース
- 東京都西東京市コワーキングスペース
- 東京都調布市コワーキングスペース
- 東京都豊島区コワーキングスペース
- 東京都足立区コワーキングスペース
- 東京都青梅市コワーキングスペース
- 法人化
- 法人口座開設
- 法人成り
- 海事代理士
- 海外企業
- 海外在住
- 海外移住
- 特許
- 生成AI
- 登記情報
- 登記簿謄本
- 目的変更
- 相続
- 社会保険
- 社労士
- 私設私書箱
- 移転登記
- 第一種動物取扱業
- 節税
- 納税管理人
- 経営管理ビザ
- 自宅マンションで登記
- 自社所有拠点
- 著作権
- 融資
- 貸し会議室
- 費用相場
- 資産管理会社
- 資金調達
- 起業スクール
- 重任登記
- 閉鎖(廃業)
- 開業
- 駐在員事務所